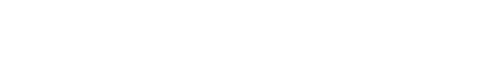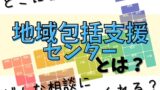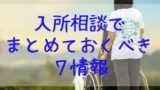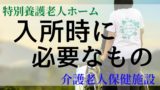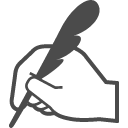家族の介護が必要になったとき、「特養(特別養護老人ホーム)」へ入所できれば良いですが、すぐに入れないのは周知の事実。
そこで登場する一案が「老健(介護老人保健施設)」ですよね。
老健(介護老人保健施設)に入所するための手続きは10ステップです。
ぬくぬくのように、働きながら家族の老健の入所手続きをする場合、2か月間ほど土日を潰して介護活動を行う必要がありました。

- 老健への入所の流れを知りたい
- 特養へ入所できなくて困っている
こんなお悩みにお答えします。
本記事をご覧の方は
という方が多いのではないでしょうか。
本記事では老健(介護老人保健施設)への入所まで、どういった流れで手続きを行っていったか、私の体験談をお伝えしていきます。

ぬくぬくが祖父を老健に入所させたときの資料をもとに解説しますよー
3分くらいで、老健(介護老人保健施設)への入所手続きの流れをイメージできますので、ご一読いただけますと幸いです。
なお、数ある介護施設の中で、老健(介護老人保健施設)の位置づけは次のとおりです。
| 公/民 | 施設の種類 | 入所可能な介護度 | 認知症対応 | 看取り |
|---|---|---|---|---|
| 公的 | 特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設) | 要介護3~5 | ○ | 施設による |
| 公的 | 介護老人保健施設 | 要介護1~5 | ○ | 施設による |
| 公的 | 介護療養型医療施設 | 要介護1~5 | ○ | ○ |
| 公的 | 軽費老人ホーム | 自立~要介護3 | 軽度まで可 | × |
| 公的 | ケアハウス | 自立~要介護3 | 軽度まで可 | × |
| 民間 | 介護付有料老人ホーム | 自立~要介護5 | ○ | 施設による |
| 民間 | 住宅型有料老人ホーム | 自立~要介護5 | 軽度まで可 | 施設による |
| 民間 | シニア向け分譲マンション | 自立~要介護5 | 軽度まで可 | 施設による |
| 民間 | グループホーム | 要支援2~要介護5 | ○ | × |
| 民間 | サービス付き高齢者住宅 | 自立~要介護3 | 軽度まで可 | × |
| 民間 | 高齢者専用賃貸住宅 | 自立~要介護3 | 軽度まで可 | × |
| 民間 | 高齢者向け優良賃貸住宅 | 自立~要介護3 | 軽度まで可 | × |
| 民間 | 健康型有料老人ホーム | 自立のみ | × | × |
老健(介護老人保健施設)とは?
老健(介護老人保健施設)とは、入所者が自宅に帰って生活ができるようになることを目指す「リハビリ」をメインにする施設です。
したがって、入所するために、以下の前提条件が発生します。
- 要介護1~5であること
- 日常の医療行為は不要であること
- 長期滞在はできない
老健(介護老人保健施設)入所までの流れ10ステップ
老健(介護老人保健施設)への入所までの10ステップをかんたんに解説していきます。
具体的にそれぞれのステップで何をするのか見ていきましょう。
老健入所ステップ①:市区町村役場、地域包括支援センターへ介護認定申請
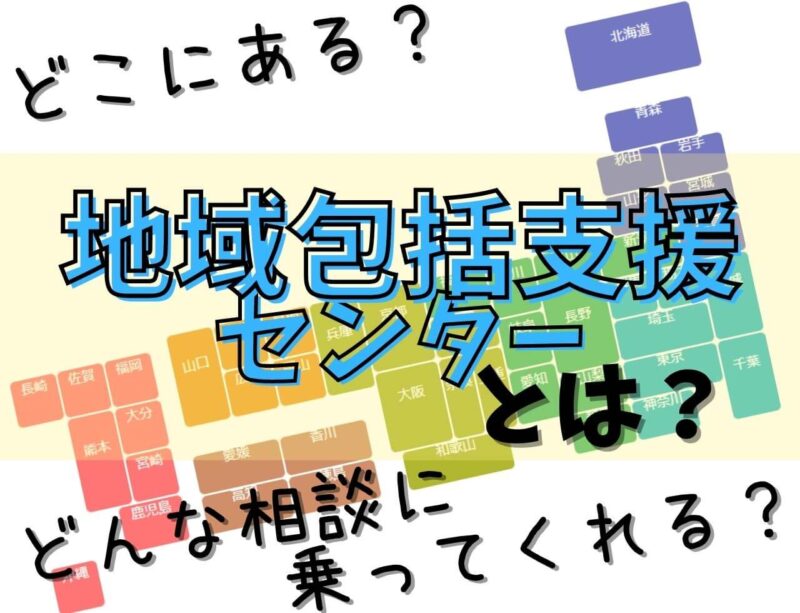
老健入所ステップ①では、市区町村役場または地域包括支援センターへ「介護認定申請」を行います。
市区町村窓口(介護福祉課など)へ電話連絡すると、介護福祉課からは、地域包括支援センターを紹介されますので、そちらにも連絡します。
それぞれの役割分担は以下のとおりです。
| 組織 | 役割 |
|---|---|
| 市区町村窓口(介護福祉課など) | 介護保険証発行 |
| 地域包括支援センター | ・介護被保険者へのヒアリング ・要介護度の判定材料準備 |
市区町村担当者や地域包括支援センターの職員と協業で手続きを進めていき、「介護保険被保険者証」を取得します。
「介護保険被保険者証」には「介護度」が記載されており、要介護1~5、要支援1~2のランク付けがあります。
状態が重い順番で
要介護5>4>3>2>1>要支援2>1
の順番です。
老健(介護老人保健施設)へ入所できる条件は要介護5~1です。
なお、私の祖父が入所していた老健(介護老人保健施設)では9割が要介護5~3の方でした。
老健入所ステップ②:介護老人保健施設へ相談
老健入所ステップ②では、介護保険施設へ電話相談します。
無事「介護保険被保険者証」を取得出来たら、インターネットでお近くの介護老人保健施設を探して、目ぼしい3つくらいの老健施設に直接電話で連絡します。
すると
「一度来訪いただいてお話させてください」
という話になりますので、老健施設の担当者と面談の日程調整します。
老健入所ステップ③:介護老人保健施設のケアマネージャーと面談
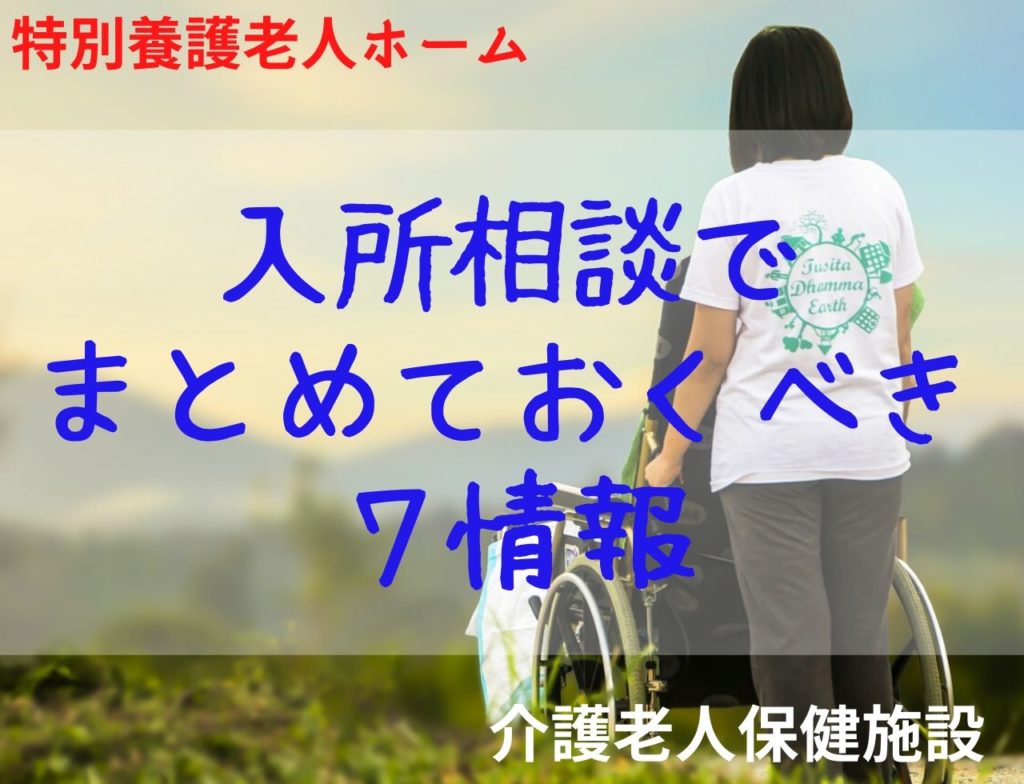
老健入所ステップ③では、老健施設の担当者と面談します。
老健の担当者に聞かれることは次の7つです。
事前に老健の面談で聞かれることをまとめておくと、どういった状況なのか、どうしたいのかを着目して相談に乗ってくれますので、おススメします。
また、面談と合わせて、施設の概要を説明いただけます。
「施設への入所申込書」も受領できますので、もらったら書いて申請します。
なお、申請して入所承認が下りても、「別の施設への入所が決まりまして」と説明すれば、入所をキャンセルできます。(むしろ普通)
老健入所ステップ④:面談後、介護老人保健施設内の見学
老健入所ステップ④では、面談後に介護老人保健施設を見学します。
面談後には「施設内を一回り見ていきましょう」という話になります。
別日にもできますが、15分程度で施設内を見学できますので、私がポイントにしていた3つの内容を参考に見学してみましょう。
- 入所した際に、どこに何を設置するか(日用品、衣類、TVなど)
- 多床室の雰囲気
- 匂い
老健見学のポイント①:入所を想定した家財や消耗品の配置
入所した際に歯ブラシなどの日用品、収納ケース必要有無、TV台の必要有無などを確認します。
老健見学のポイント②:多床室の雰囲気
多床室の雰囲気は、入居者が雰囲気よく生活しているか、入所者が馴染めるかなどの材料にします。
老健見学のポイント③:匂い
匂いは、その施設の対応をありありと表していると思います。
介護は糞尿との闘いです。アンモニア臭が色濃く漂う場合(多少は仕方ありません。どうしようもありません。)、清潔感への配慮が足りない施設と感じます。
老健入所ステップ⑤:介護老人保健施設内で判定会議

老健入所ステップ⑤では、入所申請書を提出した施設側で、受け入れできるかどうか等の判定会議が行われます。
判定会議は、施設によって日程が異なります。したがって
を、事前に確認しておくと、この施設に入所させる!という意思決定ができる日程が決められます。
もし、介護施設へ入所させたい方が入院している場合、その退院日程の目途も立てられます。
老健入所ステップ⑥:介護老人保健施設への入所決定
老健入所ステップ⑥では、老健での判定会議の結果が出ます。
めでたく入所が決定した場合、入所日程を調整して入所者を介護老人保健施設へ連れていきます。
老健入所ステップ⑦:介護老人保健施設へ介護タクシーで移動

老健入所ステップ⑦では、入所者を老健へお連れします。
介護老人保健施設は、基本的に迎えに来てくれません。
したがって家族で入所者を介護老人保健施設へ連れていきます。
介護タクシーを利用する方法もありますので、「介護タクシーを実際に利用してみた!利用方法や料金はいくら?」が参考になります。
老健入所ステップ⑧:介護老人保健施設と打合せ(介護方針協議)

老健入所ステップ⑧では、介護老人保健施設で介護してくださる各ご担当者と、介護の方針を協議します。
協議に参加する老健の担当者は次のとおりです。
- 担当窓口
- 会計・事務(利用料支払・洗濯サービス)
- 栄養士(食事)
- 介護士(支援内容)
- 医師(状態確認)
- ルーム責任者
- リハビリ士
それぞれ次の内容の確認・協議を行います。
- 医師による状態確認
- 栄養士による食事内容(きざみ食、おかゆなどなど)
- 介護士による日常支援(おむつ、排便排尿支援)・リハビリ(運動内容)など
- ルーム責任者(多床室、ユニット型の場合、実際に日頃面倒見てくれる人達)
- リハビリ士 (実際に日頃リハビリ対応してくれる人達)
老健入所ステップ⑨:介護老人保健施設内の部屋の設置
老健入所ステップ⑨では、部屋の設置を行います。
衣類などは施設の方が上手く運用してくれますが、日用品・娯楽品の設置は完全に家族対応になります。
老健入所ステップ⑩:介護老人保健施設の入所後手続き
老健入所ステップ⑩では、紙面上で契約手続きを行います。
老健入所時の契約手続きは次の4つでした。
老健契約手続き①:利用料支払い
支払方法は現金か、口座振替かどちらかでした。
口座振替にする場合、銀行印が必要になりますのでお忘れなく。
老健契約手続き②:洗濯サービス利用
入所者の衣類の洗濯を、「家族が実施する」か、「施設の委託業者に依頼する」かを選択できます。
週1訪問の予定がなければ、施設の委託業者に依頼することをおすすめします。
老健契約手続き③:介護方針承認
本日打合せした内容を書面で承認サインします。
老健契約手続き④:規約読み合わせ
施設利用にあたって規約があります。危険物持ち込みダメだよ、とか。
これも承認します。
これで、入所の手続きは完了です。
介護老人保健施設への入所手続きの流れ まとめ
いかがでしたでしょうか?
老健(介護老人保健施設)への入所手続きの流れ10ステップを改めて見てみましょう。
老健への入所手続きには、意外に時間がかかります。
土日で対応してくれる施設も多いので、土日を利用するか、有給休暇を使って確保するかして、前倒しで進めていきましょう。
入所後、用意するものが足りていないとすぐに連絡が来るようになります。
最初から必要なものがわかっていれば、その頻度も減りますが、人によって必要な物が分からないですし、後から必要になる物が出てくるのが介護です。
老健や特養に入所するときには「【介護】特別養護老人ホームや介護老人保健施設へ入所する際に必要なもの」も参考にして、事前準備していきましょう。
介護保険について知りたい方は「介護保険」は超高齢化社会の必修科目!制度やサービスのキホンの“き”に基本的なことをまとめています。
その他、介護にまつわる記事は「30代の必修科目!介護保険や介護施設入所、介護費用の情報まとめ」にまとめていますので、是非ご覧ください。

以上、ご参考になれば幸いです。