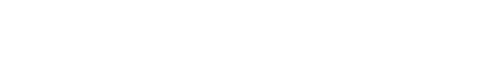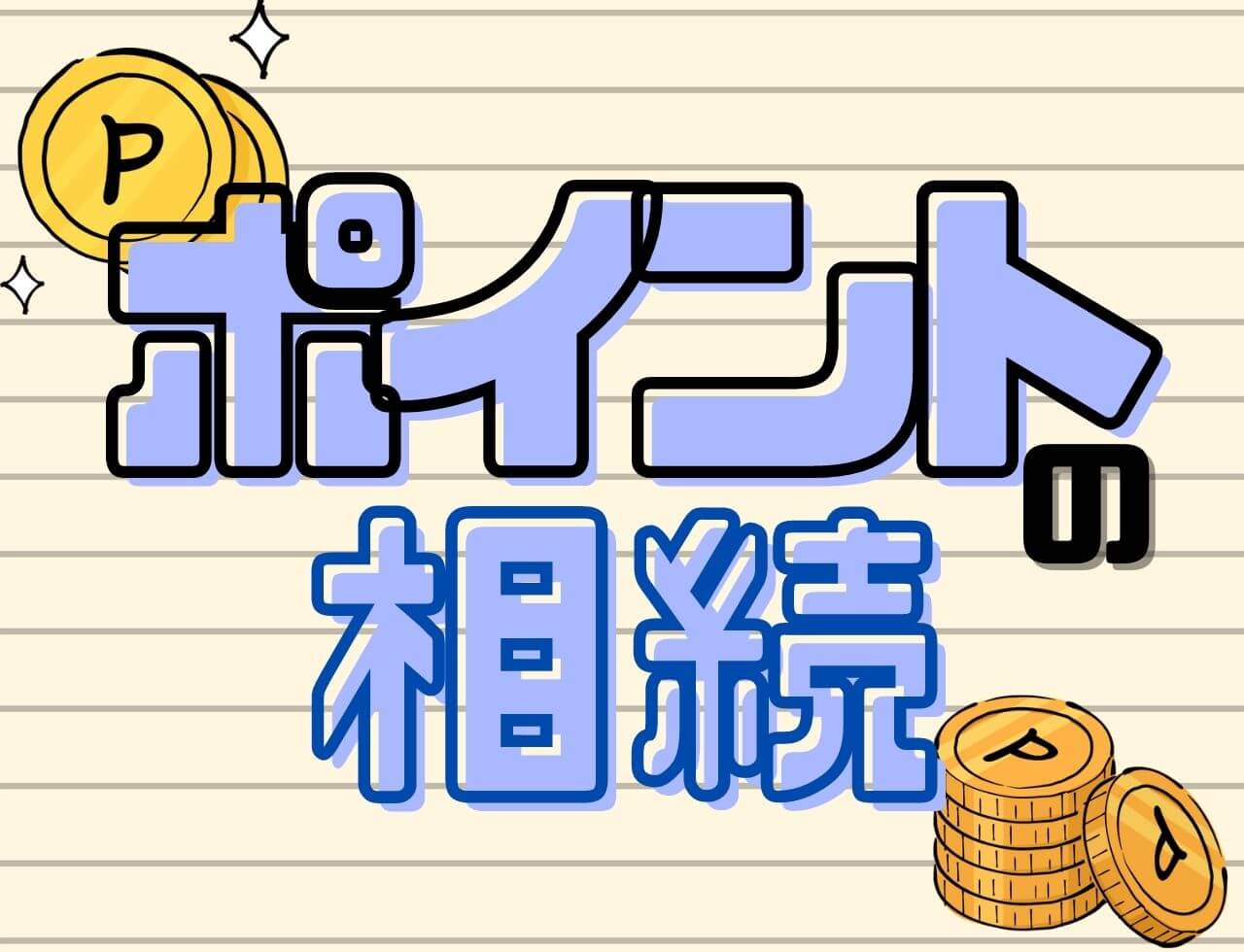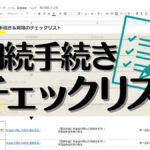ポイ活を副業にしている人も多いと思いますが、せっかくポイントも、死亡したら相続できず、失効するリスクがあるので注意しましょう。

- 4大共通ポイント(楽天ポイント・ponta・Tポイント・dポイント)やVポイントは死亡したらどうなる?
- ポイントは相続できないの?
こんなギモンにお答えします。
本記事をご覧の方は
という方が多いのではないでしょうか。
本記事では、ポイントや電子マネー、マイルの相続について解説します。

ぬくぬくもポイ活大好きです!
しかし、相続できないと知ってからは、仕組化して消費しています。
せっかく貯めたポイントも、無くなってしまったら悲しいですよね。
5分くらいで、楽天ポイント・ponta・dポイント・Tポイント・Vポイントや電子マネー、マイルの相続について理解できますので、ご一読いただけますと幸いです。
貯まったポイントは相続できない
| ポイントサービス | 相続できる? | 規約リンク |
|---|---|---|
 楽天ポイント | × 失効 | 楽天ポイント |
 Ponta(ポンタ) | × 失効 | Ponta(ポンタ) |
dポイント | × 失効 | dポイント |
 Tポイント(ティーポイント) | × 失効 | Tポイント(ティーポイント) |
Vポイント | × 失効 | Vポイント |
 PayPayポイント | × 失効 | PayPay残高 |
 LINEポイント | × 失効 | LINEポイント |
LINEPayボーナス | × 失効 (2022.8/1サービス終了) | LINEPayボーナス |
 WAON(ワオン)ポイント | × 失効 | WAON(ワオン)ポイント |
 JRE POINT | × 失効 | JRE POINT |
4大共通ポイント(楽天ポイント、pontaポイント、Dポイント、Tポイント)はもちろん、PayPayボーナスやLINEポイントなど、一般的なポイントは全て相続できません。
ポイントが相続できない理由は、民法896条に、「相続人は、被相続人の財産を相続するけど、被相続人のみ利用可能となっているものは対象外」と記載されているためです。
第五編 相続
(引用)民法第986条より
第三章 相続の効力
第一節 総則
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
また、各ポイントを利用登録するときに、「規約に同意」しており、利用者本人のみ利用できることを承認して利用しています。
したがって、ポイントは相続できません。
もし本人に成りすまして利用した場合、ポイント規約に違反することとなります。
第11条(第三者による利用)
(引用)楽天スーパーポイント規約より
ポイントの利用は、会員本人が行うものとし、当該会員以外の第三者が行うことはできません。
楽天は、ポイント利用時に入力されたIDおよびパスワードが登録されたものと一致することを楽天が所定の方法により確認した場合には、会員による利用とみなします。それが第三者による不正利用であった場合でも、楽天の責めに帰すべき事由がある場合を除き、楽天は利用されたポイントを返還しませんし、会員に生じた損害について一切責任を負いません。
また、本人の許可なくID/パスワード等を入力してポイントを不正利用した場合、「不正アクセス禁止法」に抵触する恐れがあるため、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性があります。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(引用)不正アクセス行為の禁止等に関する法律より
(罰則)
第十一条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
「ポイント運用」で貯めたポイントは相続できない

ポイント運用で得たポイントも相続できません。
ポイント運用は、ポイントをポイントのまま運用して、ポイントにしてもらえるサービスのことです。
例えば、楽天ポイントやpontaの「ポイント運用」や、dポイントの「ポイント投資(実際はポイント運用)」、PayPayボーナス運用などが該当します。
「ポイント投資」で買った投資信託は相続可能

ポイント投資で得た投資信託は「金融資産」となり相続財産となりますので、相続可能です。
例えば、楽天ポイントで購入したeMaxisSlim全世界株式や、Tポイントで購入した株や投資信託、dポイント+日興フロッギーで購入した投資信託などは、金融資産となるため、相続可能です。
失効したポイントは相続税の課税対象外!
失効したポイントは、財産を相続できませんので、相続税の課税対象外となります。
チャージした電子マネーは相続可能な場合が多い
| 電子マネー | 相続できる? | 手続き概要 | 受け取り |
|---|---|---|---|
 Suica | 〇 相続可 | 死亡した会員の退会(払いもどし)手続き のとおり。 ①書類を郵送 〒983-8561 モバイルSuicaサポートセンター宛て ②「退会・払いもどし申請フォーム」 から申請 | 現金払い戻し |
 楽天キャッシュ | 〇 | 現金払い戻し (振込手数料差引) | |
 楽天Edy | △ 遺族側で使い切り | – | |
Vポイント残高 | × 失効 | ||
 PayPay残高 ※PayPayマネー ※PayPayマネーライト | 〇 相続可 | 【電話】 PayPayカスタマーサポート窓口 電話番号:0120-990-634 窓口時間:24時間365日受付 【メール】 PayPay問い合わせフォーム | 現金払い戻し (振込手数料差引) |
LINEMoney | 〇 相続可 | LINE Pay決済サービスでお問い合わせ | ? |
LINECash | × 失効 | – | |
 nanaco(ナナコ) | × 失効 | – | |
 WAON(ワオン)残高 | △ 遺族側で使い切り | – |
電子マネーは、「現金」という性質上、相続可能な場合が多くなります。
代表的な交通系電子マネー「Suica」は、相続人が相続手続きすれば、相続人に現金払い戻しして貰えます。
楽天キャッシュは基本型・プレミアム型のどちらでも相続できるようです。
PayPay残高のうち、銀行からチャージした「マネー、マネーライト」であれば、相続できるようです。
電子マネーの中でも相続時に失効するものもある
利用者も多い「nanaco」は、以下のポイント規約にある通り、失効します。
会員が死亡した場合には、会員資格は喪失され、一切のnanaco電子マネーサービスを利用できなくなります。この場合、nanacoカード内残高およびセンター預り残高はゼロとなり、また、現金の払戻しも行われません。
(引用)nanacoカード会員規約・特約より
相続した電子マネーは相続税の課税対象!
相続した電子マネーは、「現金」として相続税の課税対象となります。
ANAマイル・JALマイルは相続可能!
ANAマイルやJAKマイルは相続手続きすれば、相続人のマイル口座に移管する形で相続できます。
また、相続人が複数人いる場合、JALマイルだと、遺産分割協議書を作成して相続手続きすれば、複数人のマイル口座に分割して相続できます。
しかし、ANAマイルもJALマイルも、相続した月の36か月後がマイルの有効期限になりますので注意しましょう。
マイルの相続は期限内に手続きが必要
ANAマイルは、被相続人が死亡した6か月以内に手続きしないと失効してしまいます。
JALマイルには手続き期限はありません。
ANAマイルもJALマイルも、マイル自体の有効期限が切れれば失効しますので、ほったらかししないようにしましょう。
相続したマイルは相続税の課税対象!
相続したマイレージポイントは、相続財産として換算されるため、相続税の課税対象となります。
しかし、マイルに関する相続税の明確な規程は無いことから、マイルで交換可能な1マイル=1円など、交換可能相当額として現金の相続財産を換算します。
飛行機のマイレージポイントの権利者が死亡した場合に、その死亡した被相続人の相続人が、そのマイレージポイントの権利を承継して、行使できるものである場合には、その権利の価額相当額が相続財産として相続税の課税財産として、相続税の課税価格に算入されることとなります。
(引用)税務研究会より
【対策方法】ポイントはマイルに交換して相続しよう!
4大共通ポイント(楽天ポイント、ponta、dポイント、Tポイント)は、ANAマイルまたはJALマイルに交換できます。
もしたくさんのポイントを保有しているようであれば、マイルに交換して相続しましょう!
ポイ活やポイントの相続手続きが難しければ専門家へ相談しよう!
ぬくぬくのように誰に相談していいかわからない!と思ってしまったら、相続サポートなどの専門家へ必ず相談しましょう。

ちなみにぬくぬくは、司法書士に、登記申請書の確認をしてもらいました。
その後、自分で相続登記をオンライン申請したため、費用は発生しませんでした。
相続に関する情報は「相続まとめ」にまとめていますので、是非ご覧ください。